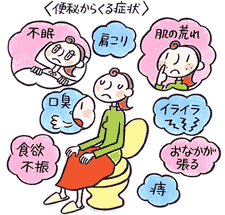 便の回数には健康な人でも個人差があるもので、習慣や職業などによっていろいろ異なり、どんな程度の便秘であるか知る必要があります。
便の回数には健康な人でも個人差があるもので、習慣や職業などによっていろいろ異なり、どんな程度の便秘であるか知る必要があります。わかばだより No.47
2004年1月
今回は、便秘に悩む方々へ、生活上の工夫と下剤の使い方について紹介します。
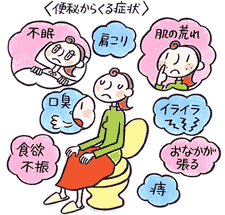 便の回数には健康な人でも個人差があるもので、習慣や職業などによっていろいろ異なり、どんな程度の便秘であるか知る必要があります。
便の回数には健康な人でも個人差があるもので、習慣や職業などによっていろいろ異なり、どんな程度の便秘であるか知る必要があります。
以下の状態を便秘と呼びます。
| 1)弛緩性便秘 | 大腸の緊張が緩んでいて、腸の動きが弱く、便意を感じなくなっています。便秘の多くはこのタイプです。 |
| 2)直腸性便秘 | 便が直腸に達しても便意が起きず、腸の運動が始まらないような便秘です。 |
| 3)痙攣性便秘 | 大腸の運動が強すぎて、けいれんを起こし、便の通過を妨げてしまう便秘です。 |
腸管が狭くなり内容物が通りにくいために起きる便秘。
甲状腺機能低下、 糖尿病などに合併して起こる便秘です。
抗精神薬、抗うつ薬、 リン酸コデインなど薬剤の副作用として起こる便秘です。
☆便秘の治療には下剤を用いるとともに、生活改善が大切です。☆
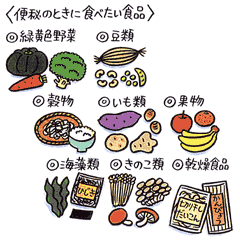 乳酸菌や酵母による発酵食品 (チーズ・ヨーグルト・キムチ・味噌・納豆)
乳酸菌や酵母による発酵食品 (チーズ・ヨーグルト・キムチ・味噌・納豆)
これらの食品を食べ過ぎると良くない人もいます。医師、栄養士から指導されている方は、そちらを優先して下さい。
食物繊維を十分に摂る生活は、大きな価値があります。家庭の食卓では野菜や海藻をなるべくたくさん利用しましょう。
また、ご飯には胚芽米を混ぜたり、食物繊維を多く摂るために生野菜を加熱調理するなどの工夫をしましょう。
| 分類 | 薬名 | 成分 | 作用機序 | 効果・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 大腸刺激性下剤 | アローゼン | センノシド | 腸粘膜に直接作用して腸の動きを活発にする。 | 服用後6〜10時間で効果が発現する。作用が強く、習慣性がある。センノシドは尿の色が黄褐色または赤色となる。 |
| センノサイド錠 | ||||
| センノサイド液 | ||||
| シンラック | ピコスルファートナトリウム | |||
| セチロ | 大黄、 酸化マグネシウム |
大腸を刺激する作用と便をやわらかくする作用の両方がある。 | 腎機能の低下してる人には注意。作用は弱く、長期に使える。 | |
| 塩類下剤 | 酸化マグネシウム | 酸化マグネシウム | マグネシウムにより、腸内の水分量を多くし、便が水様化されて容積も大きくなり大腸を刺激して排便させる。 | |
| 膨張性下剤 | D−ソルビトール | ソルビトール | 水分保持作用によって、糞便をやわらかくする。 | 胃のレントゲン検査ではバリウムを排泄させるために、服用することもある。作用は弱い |
| 浸潤性下剤 | ベンコール錠 | ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム、 カサンスラノール |
硬い便に水分を吸収させて軟便化させる。 | 作用は弱い |
| グリセリン浣腸 | グリセリン | 直腸を刺激し、大腸の蠕動運動を誘発する。 | 使用後、速やかに効果発現。内服で効果が無い場合に用いる。 | |
| 新レシカルボン坐薬 | 炭酸水素ナトリウム、 リン酸水素ナトリウム |
腸内に炭酸ガスを発生させ、その刺激により腸を活発にして排便を促す。 | 使用後15〜20分で効果発現。冷所に保存する。 |
漢方薬は作用機序が明らかでないことがありますが、西洋医学の便秘薬でうまく効果が得られない人でも、効果がある場合もあります。
食事や体調管理もし、他の薬でコントロールがうまくいかないときは医師にご相談して下さい。
| 防風通聖散 | 肥満の人の便秘 |
| 三黄瀉心湯 | 高血圧症で便秘の人、不眠傾向の人 |
| 潤腸湯 | 高齢者や皮膚がカサカサしているタイプの人 |
| 麻子仁丸 | 体力がなく、冷え症で排尿が近いタイプ、または便が硬くてコロコロしたタイプ |
| 桃核承気湯 | 比較的体力があり下腹部の圧痛や生理不順の人の便秘 |
