★今回は、総合感冒薬についてです★
冬は風邪をひく方が多い季節ですね。早く治そうと、市販の風邪薬を買う方も多いのではないでしょうか。
総合感冒薬は熱・鼻水・喉の炎症・咳といったいろんな症状に効くように、何種類もの薬が混ざっています。
中には今の症状に必要なかったり、普段飲んでいる薬や病状に合わない成分が入っていることがあります。手軽に手に入るものですが、注意が必要です。
【風邪薬に含まれる成分】
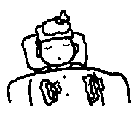 ☆ 熱や痛みを和らげる
☆ 熱や痛みを和らげる
・ アスピリン、エテンザミド、イブプロフェン
〔非ステロイド系消炎鎮痛剤〕
・ アセトアミノフェン〔非ピリン系〕
・ イソプロピルアンチピリン〔ピリン系〕 など
注意!! 非ステロイド系消炎鎮痛剤は胃腸障害を起こしやすいので、空腹時には飲まないようにしましょう。副作用で喘息が起こることがあるので(特にアスピリン、イブプロフェン)、喘息の人は注意が必要です。また、アスピリンは15歳以下の子供には飲ませないようにして下さい。
☆ 咳を和らげる
・ リン酸ジヒドロコデイン、ノスカピン、リン酸ジメモルファン
臭化水素酸デキストロメトルファン〔中枢性鎮咳薬〕
・ 塩酸メチルエフェドリン〔交感神経興奮薬〕
・ ヒベンズ酸チペピジン〔その他〕 など
注意!! 中枢性鎮咳薬は、副作用で便秘になることがあるので、普段から便秘がちな人や胃腸、痔疾患のある人は注意が必要です。また痰がきれにくくなるので、気管支喘息発作のある人は避けたほうがよいでしょう。
交感神経興奮薬は、高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能亢進症の人は注意が必要です。また、頭痛、めまい、発汗、不眠などがみられることがあります。
ヒベンズ酸チペピジンは咳を鎮める作用のほかに去痰作用もあります。この薬は尿が赤くなることがありますが心配ありません。
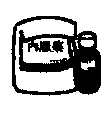 ☆ 痰を切れやすくする
☆ 痰を切れやすくする
・ グアヤコールスルホン酸、グアイフェネシン、
塩酸ブロムヘキシン など
☆ くしゃみ・鼻水・鼻づまりを和らげる
・ マレイン酸クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、
フマル酸クレマスチン、マレイン酸カルビノキサミン、
〔抗ヒスタミン薬〕 など
注意!! 眠気や喉の渇きといった症状がでることがあります。
また前立腺肥大症や緑内障の症状を悪化させる場合があるので、服用する前に主治医に相談するようにしましょう。
☆ 炎症を和らげる
・ 塩化リゾチーム、ブロメライン〔消炎酵素剤〕
・ トラネキサム酸〔抗プラスミン剤〕
・ 非ステロイド系消炎鎮痛薬 など
注意!! 塩化リゾチームは卵アレルギーの人は飲まないでください。
ブロメラインは鼻出血などの出血傾向が現れることがあります。
☆ 眠気を防ぐ
・ (無水)カフェイン、安息香酸ナトリウムカフェイン など
注意!! 紅茶やコーヒーなどカフェインを多く含む食品と一緒に摂ると、動悸がしたり、眠れなくなることがあります。
◆葛根湯について
葛根湯には、葛根(かっこん)、麻黄(まおう)、桂皮(けいひ)、生姜(しょうきょう)、大棗(たいそう)、芍薬(しゃくやく)、甘草(かんぞう)の生薬が含まれています。
葛根、麻黄、桂皮、生姜は体を温め、発汗、解熱作用があります。
この他に、葛根はこりをほぐす作用、麻黄は主成分がエフェドリンで、鎮咳・去痰作用があります。エフェドリンは心臓疾患や高血圧のある人が服用すると、病状を悪化させる可能性もあります。
大棗、芍薬は滋養強壮作用、甘草は喉の痛みや咳を和らげる作用があります。甘草は大量・長期服用によるむくみに注意が必要です。
葛根湯は風邪の引き始めに適しています。発汗作用が強いため、既に発汗のある場合や体力のない人には向きません。
薬局の窓口から
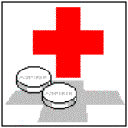 Q、最近アメリカで問題となった成分とはどんなものですか?
Q、最近アメリカで問題となった成分とはどんなものですか?
A、アメリカで問題となった成分は、
「フェニルプロパノールアミン(PPA)」というものです。PPAは鼻の充血を取り除き、鼻づまりを改善する効果があります。アメリカではその他に、ダイエット目的で食欲抑制剤として使われていました。昨年アメリカの大学から、PPAを飲んでいる人の方が、飲んでいない人よりも脳出血を起こす確率が高いという研究発表があったため、アメリカでは使用中止を勧めています。日本では、使用量がアメリカよりも少ない(アメリカは1日最大150mg、日本は100mg)ので使用中止にはなっていませんが、高血圧の人や脳出血を起こしたことのある人は使用しないように呼びかけています。服用中にはげしい頭痛、動悸、不眠、神経過敏などの症状がでたら、すぐ中止するようにしましょう。

編集後記
総合感冒薬は、風邪による不快な症状を和らげ日常生活にも速やかに移行できるようになることが期待できます。しかし、総合感冒薬はあくまで対症療法であり、風邪を治すには安静・保温・水分補給が重要です。一般に風邪は1週間程度で治ることが多いので、何日も熱が続いたり、薬を飲んでも症状が改善しないようなときは、医師の診察を受けるようにしましょう。〈Y〉
参考資料
- 調剤と情報 1999年12月号
- OTCハンドブック1997−1998
- 塩酸フェニルプロパノールアミン(PPA)含有製剤に関する情報 (Kumamoto Pharmaceutical Association)
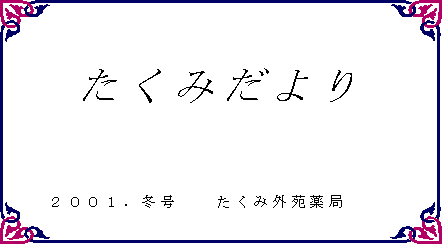
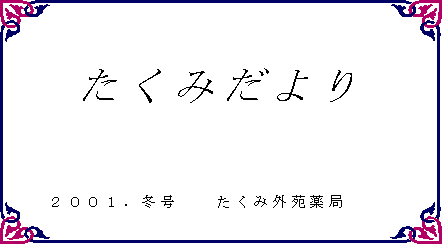
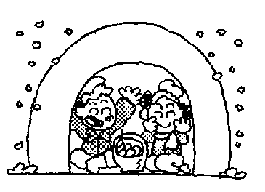
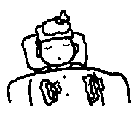 ☆ 熱や痛みを和らげる
☆ 熱や痛みを和らげる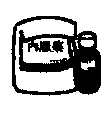 ☆ 痰を切れやすくする
☆ 痰を切れやすくする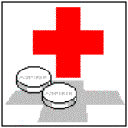 Q、最近アメリカで問題となった成分とはどんなものですか?
Q、最近アメリカで問題となった成分とはどんなものですか?