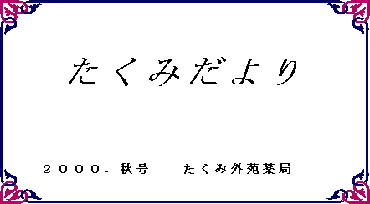 |
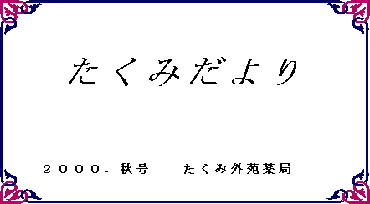 |
ビタミンは、人が健康であるためにはなくてはならないものです。毎日バランスの良い食事をとっていれば問題はないのですが、食生活が偏っている人や食事制限のある人ではビタミンが不足して体に何らかの症状が出てきます。ただし、多く摂れば良いわけでもなく、かえって害になることもあります。
今回は、どんなビタミンがどんなはたらきをしているのか、どんなことに気を付けなければならないのかを紹介します。
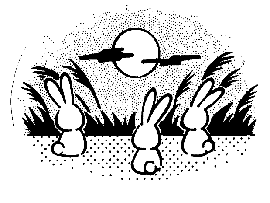 |
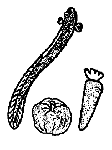 体内のビタミンAは主に肝臓に蓄えられます。そのため、魚の肝油や牛のレバーに多く、他にもうなぎや卵黄などの動物性食品に含まれます。植物性食品でも、腸でビタミンAに変わるβカロチンを含む緑黄色野菜や果物から補うことができます。ビタミンAは、目の神経を作るはたらきがあるため、欠乏すると薄暗いところで物が見えなくなる夜盲症がおこってきます。
体内のビタミンAは主に肝臓に蓄えられます。そのため、魚の肝油や牛のレバーに多く、他にもうなぎや卵黄などの動物性食品に含まれます。植物性食品でも、腸でビタミンAに変わるβカロチンを含む緑黄色野菜や果物から補うことができます。ビタミンAは、目の神経を作るはたらきがあるため、欠乏すると薄暗いところで物が見えなくなる夜盲症がおこってきます。
逆に摂りすぎると、食欲不振、頭痛、脱毛などがあらわれます。特に妊娠中の女性は、赤ちゃんに影響がでるので注意しましょう。ただし、βカロチンの場合は、ゆっくりビタミンAに変わって消費されるので、摂りすぎになることはないようです。
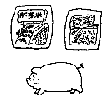 【医薬品名:アリナミンF,ジセタミン】
【医薬品名:アリナミンF,ジセタミン】
ビタミンB1は、体内で糖からエネルギーを作り出す反応に欠かせません。豚肉や豆類や胚芽米などに多く含まれますが、他にもいろいろな食べ物に含まれているので不足することはまれです。ただし、発熱や妊娠などビタミンの消費が増える場合は、不足して疲れやすくなったり、食欲低下やむくみなどの症状がおこります。
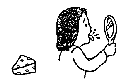 【医薬品名:ハイボン】
【医薬品名:ハイボン】
ビタミンB2はエネルギー産生やアミノ酸代謝に関わるビタミンです。レバーや乳製品に多く含まれ、不足すると唇や舌が荒れてきます。
玄米、肉、魚などのさまざまな食品に含まれ、アミノ酸代謝に関わるビタミンです。体内のビタミンB6を使い果たすような薬物(イスコチン、アプレゾリンなど)や遺伝的要因によって不足すると、貧血、皮膚炎、けいれんなどがおこります。
【医薬品名:レチコラン,ハイコバール】
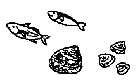 レバーや魚介類などの動物性食品に含まれ、普通の食事で十分補えるものですが、胃を切除した人ではビタミンB12 が吸収されないため、欠乏症が起こりやすくなります。ビタミンB12は、葉酸とともに正常な赤血球の形成やDNAの合成に関わり、どちらか一方でも欠乏すると、赤血球が肥大する貧血(悪性貧血)がおこります。
レバーや魚介類などの動物性食品に含まれ、普通の食事で十分補えるものですが、胃を切除した人ではビタミンB12 が吸収されないため、欠乏症が起こりやすくなります。ビタミンB12は、葉酸とともに正常な赤血球の形成やDNAの合成に関わり、どちらか一方でも欠乏すると、赤血球が肥大する貧血(悪性貧血)がおこります。
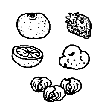 みかんやいちごなどの果物、キャベツやじゃがいもなどの野菜に多く含まれ、鉄の吸収や骨や皮膚などの組織形成に欠かせません。欠乏すると、歯茎や皮下などに出血がおこり貧血になります(壊血病)。逆にたくさん摂りすぎると、下痢になったり、腎臓結石を生じる場合もあります。また、ビタミンC自身は、酸化されやすく熱で壊れやすい性質を持っているため、調理する時に注意が必要です。
みかんやいちごなどの果物、キャベツやじゃがいもなどの野菜に多く含まれ、鉄の吸収や骨や皮膚などの組織形成に欠かせません。欠乏すると、歯茎や皮下などに出血がおこり貧血になります(壊血病)。逆にたくさん摂りすぎると、下痢になったり、腎臓結石を生じる場合もあります。また、ビタミンC自身は、酸化されやすく熱で壊れやすい性質を持っているため、調理する時に注意が必要です。
ビタミンDには、日光に当てたきのこ類に含まれるD2と、レバーや卵黄に含まれるD3があります。腸管からのカルシウムの吸収を高めて骨をつくるはたらきがあります。ビタミンDが欠乏すると骨のカルシウムが不足して、骨が柔らかくなる病気になります。逆に、摂りすぎると腎臓にカルシウムがたまり、のどが渇いたり食欲が低下したりします。
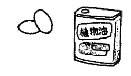 【医薬品名:ニチEネート】
【医薬品名:ニチEネート】
植物油や豆類、卵黄などに含まれます。抗酸化作用があり、体の細胞が傷つくのを防ぎます。不足すると、赤血球が壊れて貧血になったり、神経に異常がおこったりします。
緑の野菜や植物油などに含まれ、一部腸内でつくられます。血液を固めるはたらきがあるため、不足すると出血しやすくなります。
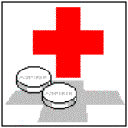 Q、病院でビタミン剤をもらってのんでいます。摂り過ぎになりませんか?
Q、病院でビタミン剤をもらってのんでいます。摂り過ぎになりませんか?
A、過剰になりやすいビタミンとして、脂溶性のため体内に残りやすいビタミン(A、D、E、K)があります。1日の必要摂取量の10倍以上を摂取した場合、ビタミンAとDは過剰症が問題となることがありますが、ビタミンEとKは問題ありません。水溶性ビタミンのなかでもビタミンB6やCはまれに過剰症がでることがありますが、その他のビタミンは問題ありません。
医師の指示のもとで服用しているビタミン剤は、治療に必要なものなので、摂り過ぎになることはまずないでしょう。ビタミンの摂り過ぎになりやすいのは、市販のビタミン剤を多量に服用している場合です。指示された量をきちんと守って飲むようにしましょう。
